「震源地ゲーム(しんげんちゲーム)」は、観察力・集中力・協調性を育てられる集団あそびとして、保育園や幼稚園でも人気の遊びです。
道具を使わず、輪になって楽しめるため、雨の日の室内あそびや集団活動の導入にもぴったり。
この記事では、震源地ゲームの基本ルールや遊び方、対象年齢ごとの工夫、発達につながるねらい、盛り上がるアレンジ例まで詳しく紹介します。
☆実際に私が保育園で働いていた時の内容やアイディアも紹介していきますね!
震源地ゲームとは?

簡単なルールで盛り上がる!人気のグループ遊び
震源地ゲームとは、一人が“震源地”となり、動きをこっそり変化させることで、それを周囲の人がまねしていくゲームです。
「誰が震源地か」を当てる推理要素があるため、子どもたちは夢中になって遊びます。
ルールが簡単で、準備も不要。保育園・幼稚園だけでなく、小学生のアイスブレイクにも使われる定番の集団あそびです。
どんな場面で使える?保育園・幼稚園での導入例
- 朝の会・帰りの会の導入として、集中を高めたいとき
- 雨の日など、室内で身体を動かしたいとき
- 異年齢交流やグループ活動のきっかけづくりに
人数が多くても全員で楽しめるので、発表会練習の合間や行事の前後など、リフレッシュタイムにもおすすめです。
☆私は雨の日の室内遊びの時間に取り入れる事が多かったです。個々で遊べる自由遊びの時間とみんなで一緒に遊ぶ時間を設ける時に遊ぶことが多かったです。
震源地ゲームの基本の遊び方とルール

準備するもの
- 特に必要な道具はありません。
- 遊ぶスペース(輪になれる広さ)があればOKです。
基本ルール(シンプル版)
- みんなで輪になります。
- 1人“鬼役(観察者)”を決めて、鬼はその場を少し離れます。
- 残ったみんなの中から1人“震源地(リーダー)”を決めます。
- 震源地は、手拍子・肩たたき・足踏みなど簡単な動きを始めます。
- 他の人たちはその動きをまねして一緒に続けます。
- 鬼は戻ってきて、「誰が震源地なのか」を観察して当てます!
このとき、震源地はできるだけ自然に動きを変えるのがポイント。
まねしている人たちも、バレないようにすぐに反応するのがコツです。
遊び方の流れ(ステップごとに紹介)
- 鬼役が外に出ている間に震源地を決定
- 震源地が最初の動きをスタート(例:手をたたく)
- 他の子どもたちはリーダーを見ながらまねを始める
- 鬼が戻り、みんなの様子をよく観察
- 震源地が動きを変えるたびに全員がまねる
- 鬼が「○○ちゃんが震源地!」と指名
- 当たったら交代、外れたらもう一回チャレンジ
シンプルながら、観察力や反応力が試されるゲームです。
年齢別に楽しむ震源地ゲームの工夫
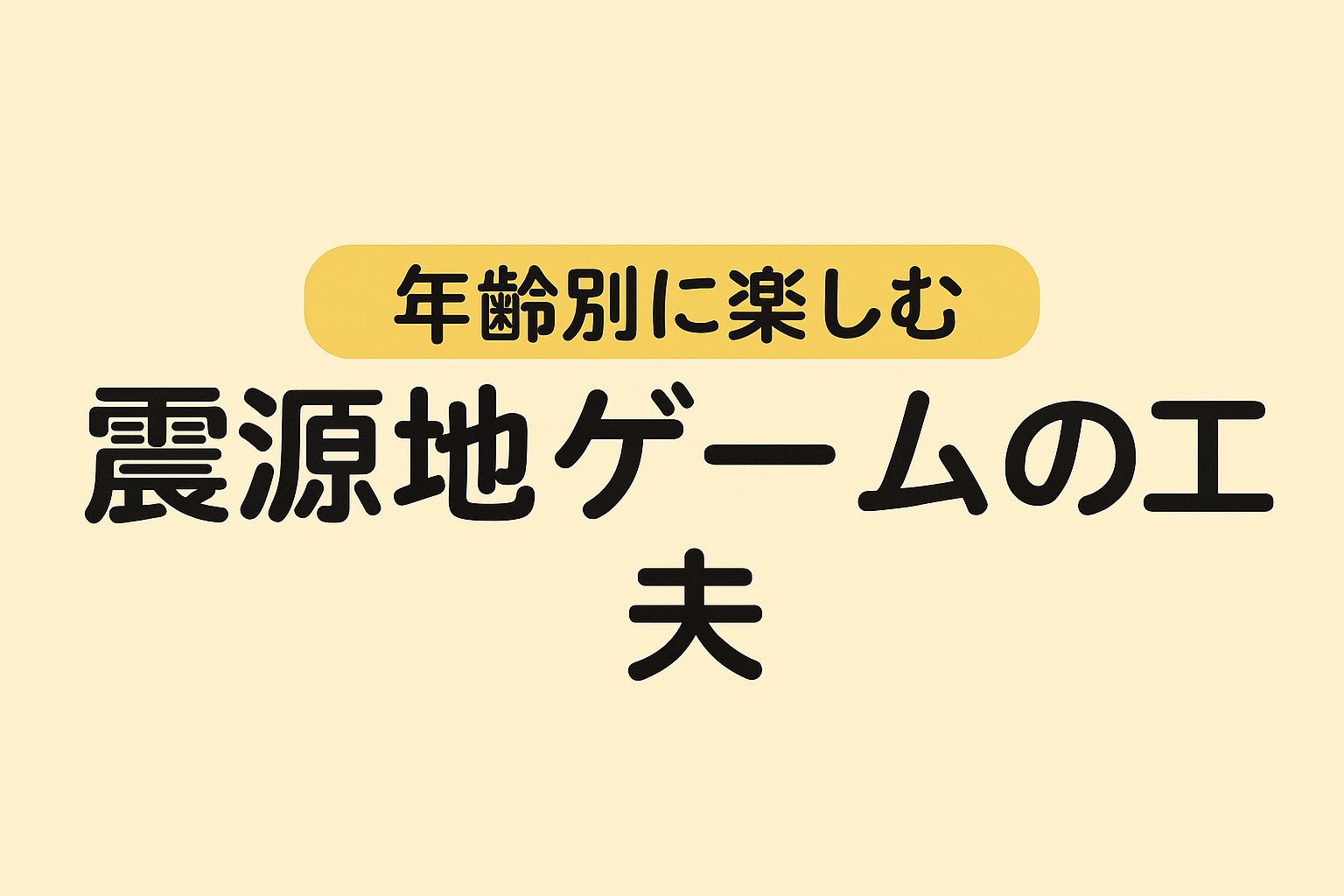
3歳児〜(簡単な動き中心・まねっこ遊びとして)
3歳ごろの子どもには、“まねっこあそび”として楽しむのが◎。
鬼役をなくして、みんなで「先生のまねっこをしよう!」とするだけでも十分楽しめます。
動きの例:
- 手をたたく
- 頭をさわる
- ぐるぐる回る
- にっこり笑う
まだ“誰が震源地か”を推測するのは難しいため、まずはまねる楽しさを感じられるようにします。
4歳児〜(観察力や集中力を育てる)
4歳児クラスでは、鬼役を取り入れて「誰が震源地かな?」と当てるルールを導入します。
子どもたちは周囲をよく観察するようになり、集中して動きを見る力が育ちます。
コツは、動きの難易度を少しずつ上げること。
たとえば、「肩たたき → 腰ふり → 拍手」など、リズムに変化をつけると飽きずに楽しめます。
5歳児〜(推理やチームワークを楽しむ応用ルール)
5歳児以上では、ルールを応用して推理要素やチームプレーを加えるのがおすすめ。
応用ルール例:
- 鬼を2人にして観察力を競う
- 音楽を流しながら、リズムに合わせて動きを変える
- 震源地を途中で交代して、より難しくする
「どうやって動きを隠すか」「みんなにうまく伝えるか」を考えることで、コミュニケーション力や表現力も高まります。
☆今でも覚えているエピソードとしては、子ども達が震源地になって遊んでいたのですが、震源地の子の表情や周りの子がその子を思いきり見ていたので、動きというよりどこに顔を向けているのかで気づかれてしまっていました。
その子は必死に気づかれないようにしていたのに、周りの子で気づかれてしまうのも微笑ましかったですね。
保育でのねらいと発達への効果
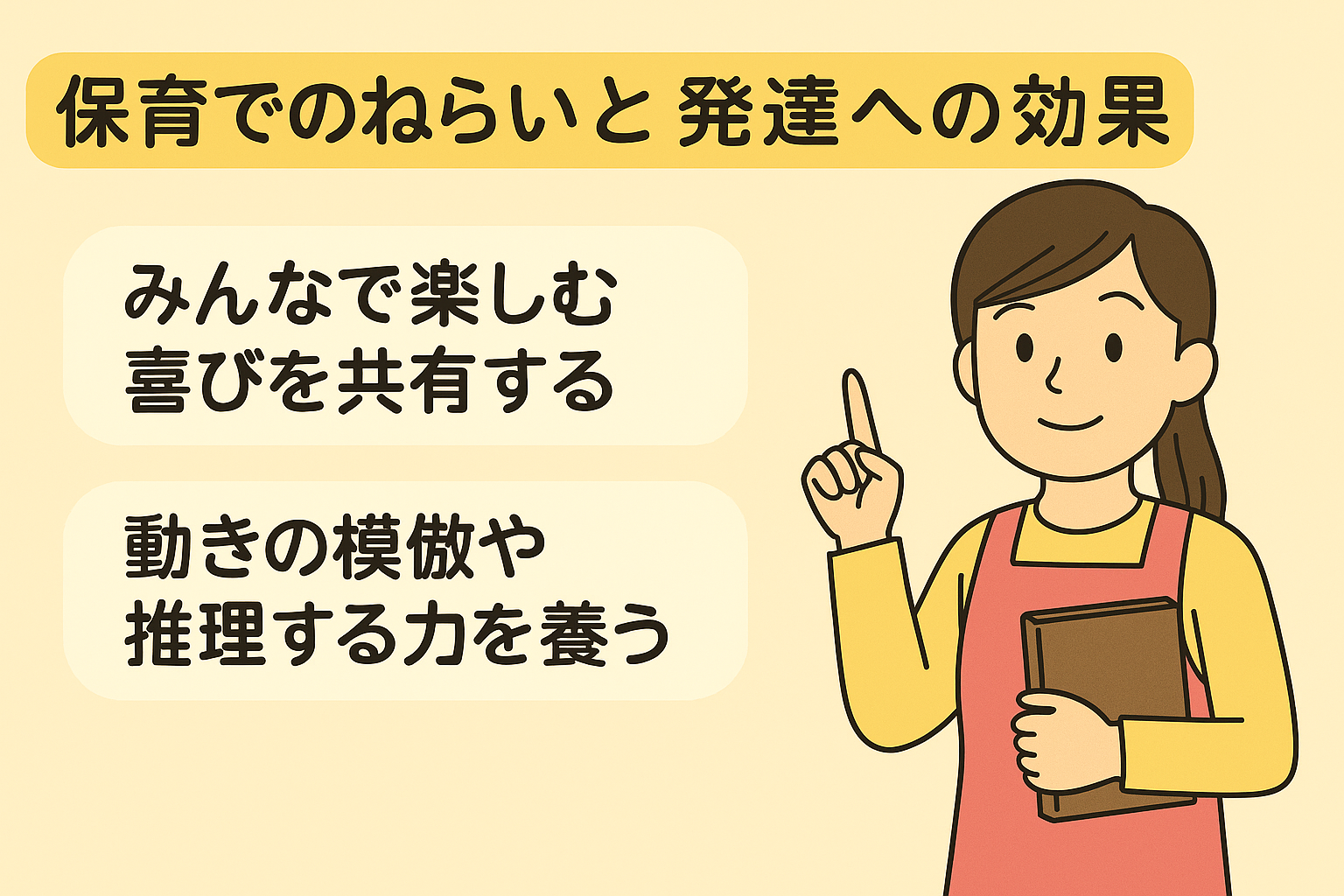
友達同士のコミュニケーションを深める
震源地ゲームは、言葉を使わずに通じ合う体験ができる遊びです。
まねをする・される関係の中で、友達への関心が高まり、自然と笑顔やアイコンタクトが増えます。
「○○ちゃんがリーダーだったんだ!」「よく見てたね!」など、会話のきっかけにもなります。
観察力・注意力・集中力が育つ
鬼役は、みんなの動きをじっくり観察しながら、わずかな手がかりを頼りに震源地を見つけます。
「だれが最初に動きを変えたかな?」という細かい観察を通して、注意深く見る力・集中する力が養われます。
集団遊びを通して協調性や達成感を味わう
全員が協力して1つの動きを続けるため、自然とチームワークや協調性が育ちます。
また、「バレずにできた!」「当てられた!」といった結果に一喜一憂する中で、遊びを通じた達成感や満足感も味わえます。
盛り上がるアレンジ&バリエーション例
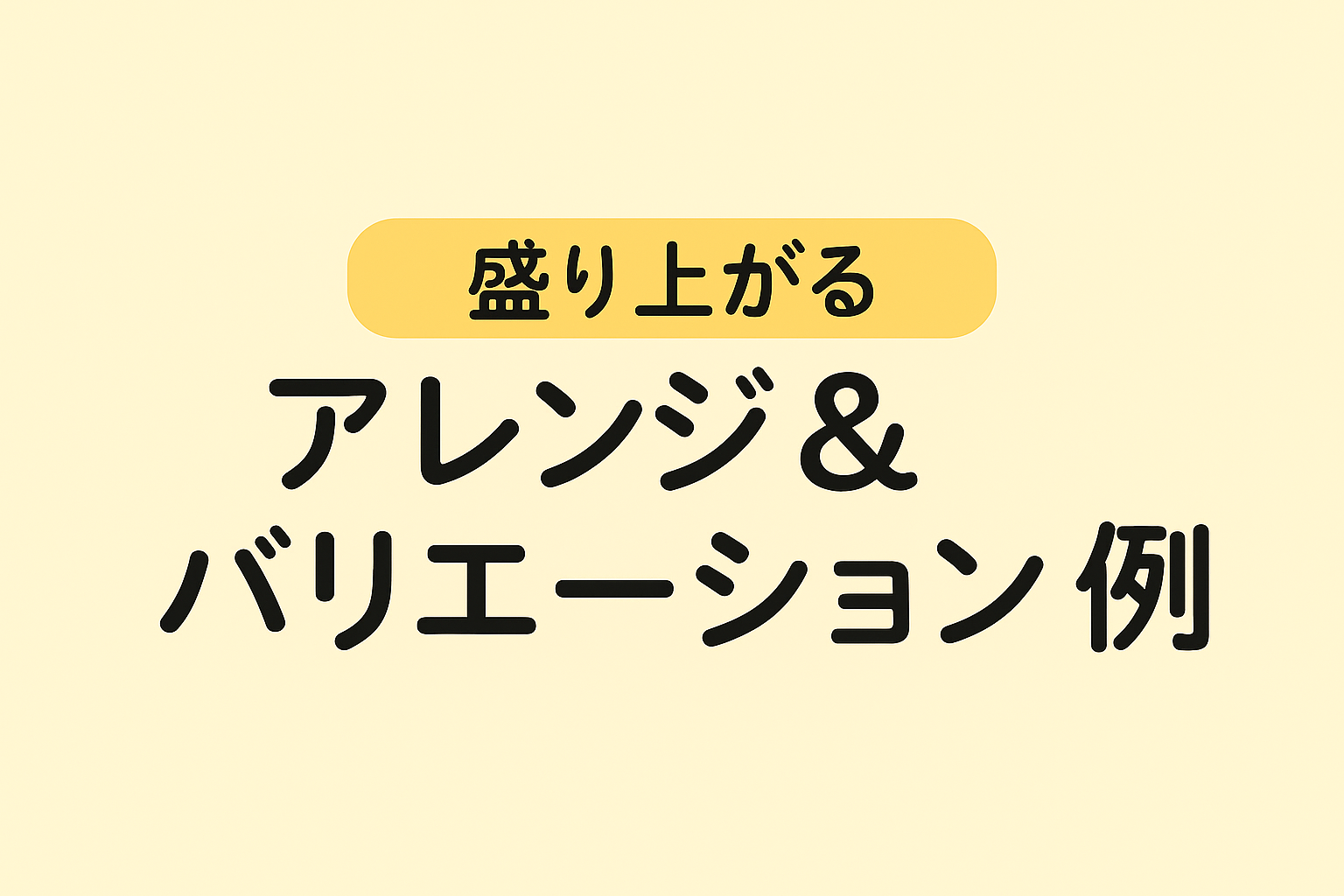
動きやジェスチャーを季節行事に合わせてアレンジ
季節のテーマを取り入れると、より楽しく盛り上がります。
- 12月:サンタの「プレゼントを運ぶ」「ベルを鳴らす」ポーズ
- 2月:鬼の「豆まき」「ポーズ」
- 5月:こいのぼりの「泳ぐまね」
季節ごとに“動き”を変えるだけで、年中通して取り入れやすくなります。
音楽やリズムを取り入れてより楽しく
BGMをかけてリズムに合わせて動くと、リトミック的な要素も加わり、体を動かす楽しさがアップ。
テンポを変えたり、曲の途中で止まるタイミングに合わせて震源地が動きを変えるなど、音楽遊びとしても応用できます。
全員が参加できるように工夫するアイデア
- 鬼が当てたら次の鬼をその人が選ぶ(順番制よりスムーズ)
- 集まりが苦手な子も安心できるよう、最初は先生が震源地に
- 難しい動きは避け、体全体を使うシンプルなものを中心に
少しずつ慣れてきたら、子どもたち自身で鬼や震源地を決めさせると、遊びの主体性も育ちます。
まとめ|震源地ゲームで“みんなが主役”の時間を楽しもう
震源地ゲームは、子どもたちの観察力・集中力・コミュニケーション力を育てる、保育にぴったりの集団あそびです。
ルールが簡単で準備も不要、少人数でも大人数でも楽しめる万能な活動として、日々の保育や室内遊びの定番にできます。
少しの工夫で年齢や発達段階に合わせて遊べるので、
「どんな子も主役になれるあそび」として、ぜひ園で取り入れてみてください。
✨ ポイントまとめ
- 対象年齢:3歳〜(年齢に応じてルール調整可)
- 準備物:不要(輪になれるスペースだけ)
- 育つ力:観察力・集中力・協調性・表現力
- 活用場面:朝の会/室内あそび/異年齢交流など









コメント