発表会は、1年を通して子どもの成長を一番感じられる行事のひとつ。
子どもたちが一生懸命に練習し、保護者の前で堂々と披露する姿は、保育士にとっても感動の瞬間です。
そんな発表会で欠かせないのが、「コメント」。
プログラム紹介や発表後の言葉、お便りに添えるメッセージなど、保育士が言葉で伝えることで、保護者に“成長の背景”や“感謝の気持ち”を届けることができます。
この記事では、現場でそのまま使えるコメントの書き方と例文を、年齢・場面別に紹介します。
☆実際にコメント一つ一つの言葉が保護者の心に残ったという実感をした事があるので、お伝えしていきますね。
発表会コメントとは?目的と伝えるべきポイント
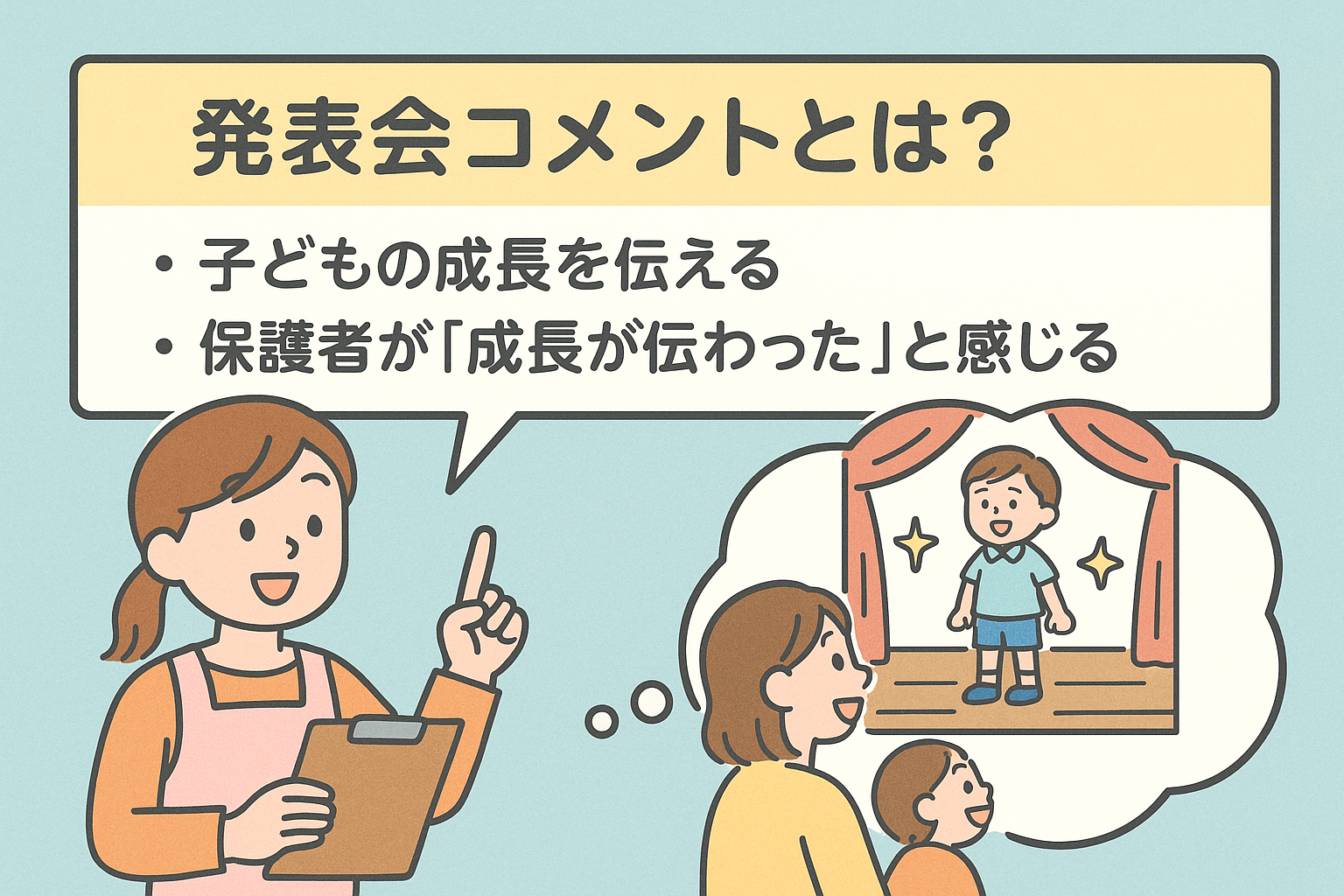
コメントは「子どもの成長」を言葉で伝える大切な場面
発表会コメントの目的は、単にプログラムを紹介することではなく、子どもの成長を言葉で表現すること。
緊張しながらも頑張る姿や、友達と協力して作り上げた過程を伝えることで、保護者に「子どもたちの頑張りが伝わった」と感じてもらえます。
保護者・子ども・同僚、誰に向けて書くかを意識しよう
コメントを書くときは、誰に向けて伝えるのかを意識すると言葉が自然になります。
たとえば発表会当日のあいさつなら“保護者全体に”、
子どもへのコメントなら“その子の努力や成長を具体的に”、
同僚へのねぎらいの言葉を加えるのも効果的です。
☆基本的には保護者向けが多いです。その場が発表会当日なのか、お便りやプログラムのような文面なのかによっても変わってきます。
伝わるコメントに共通する3つのポイント
- 具体的であること …「頑張りました」ではなく「セリフを最後まで自信を持って言えました」と具体的に。
- 温かみがあること …感情が伝わる優しい言葉を選びましょう。
- 前向きな表現にすること …失敗よりも成長に焦点を当て、「次が楽しみ」と締めると印象的です。
場面別に見る!発表会コメントの書き方と例文

① 開会・閉会のあいさつに使えるコメント例
園長や主任、担任など立場ごとに少しトーンを変えると伝わりやすくなります。
園長の例文
「本日はお忙しい中、子どもたちの発表会にお越しいただきありがとうございます。
練習を重ねる中で、できることが増え、友達と協力する姿がたくさん見られました。
どうぞ一人ひとりの成長を温かく見守りながらご覧ください。」
担任の例文
「毎日、歌やセリフを少しずつ覚えて、自信を持って舞台に立てるようになりました。
子どもたちの頑張りを感じていただけたら嬉しいです。」
閉会あいさつの例文
「緊張しながらも最後まで笑顔でやりきった子どもたちに大きな拍手をお願いします。
本日は温かい応援をありがとうございました。」
② プログラム紹介・ナレーション時のコメント例
プログラム紹介では、見どころや子どもたちの取り組み方を簡潔に伝えるのがポイントです。
例文
「次は、3歳児クラスによる『どうぶつの森のダンス』です。
みんなで動物になりきって、元気いっぱいに踊ります。
好きな動物のポーズに注目してご覧ください。」
ナレーション時の例文
「うさぎさんたちはお花を見つけて大喜び! さて、次は何をするのでしょうか?」
子どもたちが舞台裏で緊張しているときにも、ナレーションが優しい雰囲気を作ることで、会場全体が温まります。
③ 子ども一人ひとりへのコメント例(発表後のメッセージ)
発表会の後、掲示やアルバムに添えるコメントは、保護者にとって宝物になる言葉です。
0〜2歳児向け
「初めての舞台でしたが、泣かずに立つことができました。
手を振る姿がとても可愛らしかったです。」
3〜5歳児向け
「少し緊張していたけれど、最後まで笑顔でセリフを言えましたね。
友だちと心を合わせて頑張る姿に成長を感じました。」
コメントは短くてもOK。
一人ひとりの“できた瞬間”を丁寧に言葉にすることが、何よりのメッセージになります。
④ 保護者へのコメント例(お便り・掲示・アルバム用)
発表会を終えたあとのお便りには、感謝と子どもの成長を伝える一言を添えると印象が良くなります。
例文
「発表会では温かい拍手と応援をありがとうございました。
練習を通して子どもたちは新しいことに挑戦する楽しさを知りました。
舞台を終えた子どもたちの表情は、自信に満ちていました。」
保護者は“我が子の頑張り”だけでなく、“園全体の雰囲気”を知ることでも安心感を持ちます。
コメントを通して、家庭と園の信頼関係を深めることができます。
年齢別・行事別に使えるコメント文例集

乳児クラス(0〜2歳)向けコメント例
「お名前を呼ばれて手を振る姿がとても可愛かったです。」
「泣きながらも先生と一緒に舞台に立ち、頑張る姿が印象的でした。」
「音楽が流れると体を揺らしてリズムにのる姿が微笑ましかったです。」
まだ言葉で表現が難しい年齢だからこそ、“仕草や表情”を言葉にすると伝わりやすくなります。
☆この時に子ども達の日々の様子と照らし合わせながらのコメントをする事で、「日頃から子ども達の事を細かく見てくださっているんだな。」という印象にも残りますよ。実際、アンケートや連絡帳に「先生からのコメントを聞いて、日々の保育を丁寧に見てくれているのが伝わりました。ありがとうございます!」という言葉を保護者の方からいただいた事がありました!
幼児クラス(3〜5歳)向けコメント例
「自分のセリフをはっきりと大きな声で言うことができました。」
「友だちと声を合わせて歌う姿に、心の成長を感じました。」
「練習ではうまくいかなかった部分も、本番で力を発揮できました。」
成長段階に合わせて、「できるようになったこと」や「努力の過程」を具体的に入れると、保護者の胸に響きます。
☆成長過程をありのままに伝えてあげる事もポイント。良いところだけを伝えるのももちろんですが、子どもの変化が伝わるようにマイナスだった部分を軽く伝えるのもありだと私は思います。
実際にあったのが、「練習し始めの頃は遊ぶ事の方が楽しくてなかなか集中して劇練習に参加していなかった子どもが練習を重ねていくうちにリーダーシップを発揮してくれるようになり、みんなを引っ張ってくれる存在にまで成長しました。」など。
発表会テーマ別コメント例(劇・ダンス・合奏・合唱など)
劇の場合
「自分の役になりきって演じる姿が立派でした。お友だちのセリフもしっかり聞けていました。」
ダンスの場合
「リズムに合わせて笑顔で体を動かす姿に、会場中が元気をもらいました。」
合奏・合唱の場合
「お友だちと音を合わせることを楽しみながら、素敵なハーモニーを奏でていました。」
☆コメントは簡潔にどの部分を保護者に知ってもらいたいかというのもポイントの一つですね!
長ければいいという問題でもないので、コメントを考えたら、クラスの先生や園長・主任の先生に確認してもらいましょうね!
コメントを書くときの注意点とNG表現

比較・否定・上から目線にならない言葉を避ける
「〜ちゃんより上手にできた」「前より落ち着いていた」などの比較表現は避けましょう。
代わりに、「自信を持ってできた」「楽しそうに取り組んでいた」といった個人の成長に焦点を当てた表現を使うと安心です。
家庭状況・個人差に配慮した書き方を意識
発表会に参加できなかった子どもや、緊張で泣いてしまった子もいます。
「その子なりに頑張っていた」「先生と一緒に舞台に立てた」といった、“一歩踏み出せたこと”を肯定的に伝えることが大切です。
漢字・言い回し・句読点など読みやすさの工夫
保護者が読むことを前提に、ひらがなを多めに使う、文章を短く区切るなど、やさしい日本語を心がけましょう。
掲示やお便りでは「温かく・見やすく・伝わる」文章がベストです。
※文面で書く場合は必ず他の先生方にも確認をしてもらいましょう。最近は手書きよりPC入力が多くなっていると思うのですが、うっかり変換ミスが起きやすいので確認してもらうのがおすすめです!
まとめ|保育士の言葉で“子どもの成長”を温かく伝えよう
発表会コメントは、子どもたちの成長を言葉にして伝える大切な役割を担っています。
短い一文でも、先生の目で見た“頑張り”や“変化”を具体的に伝えることで、保護者に深い感動を届けられます。
発表会は、子どもにとっても保護者にとっても、1年の集大成。
保育士のコメントが、その瞬間をより輝かせるきっかけになります。
ぜひ温かい言葉で、子どもたちの成長を共有してみてください。
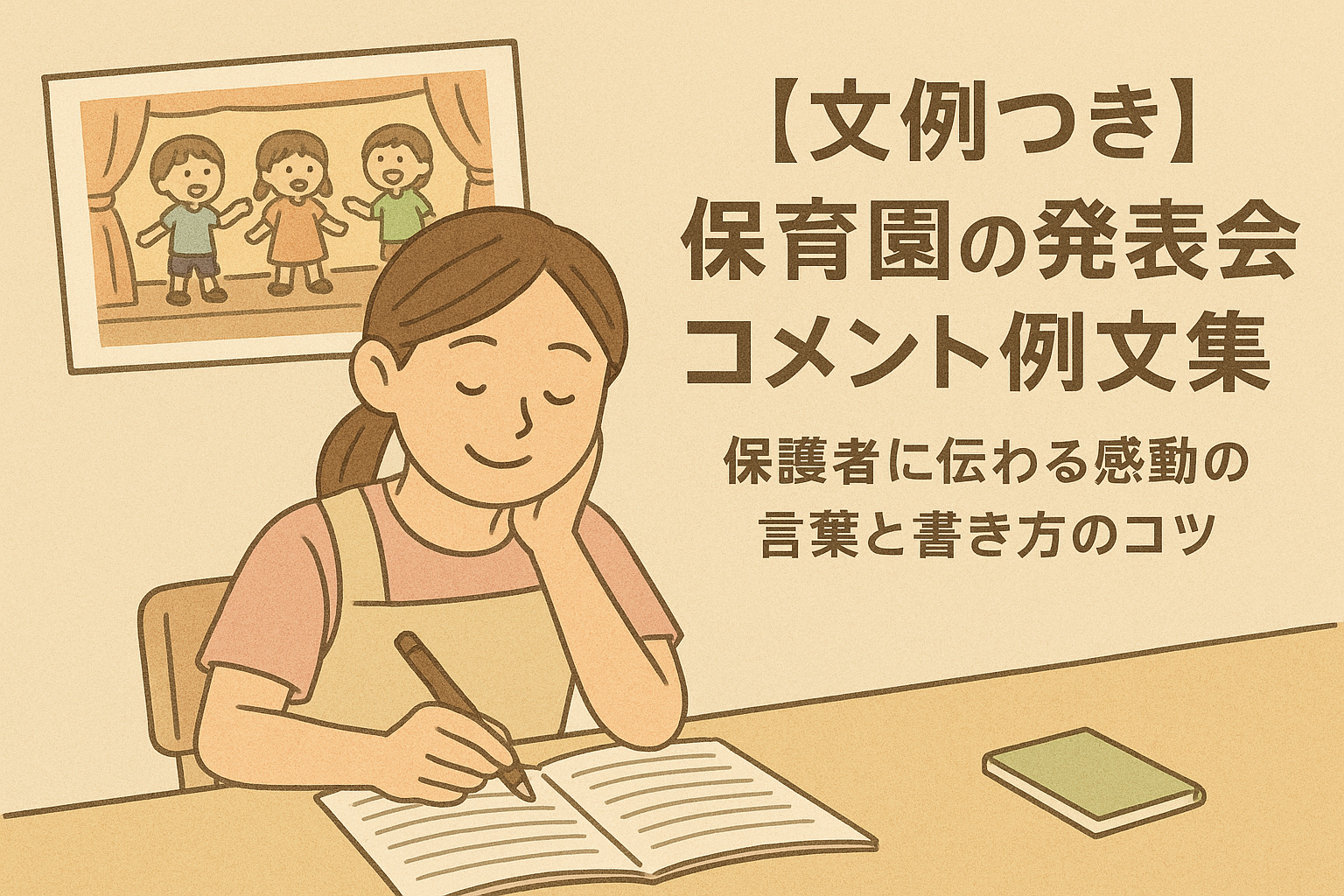








コメント