保育の現場で長年愛されている「粘土遊び」。
子どもたちが夢中になって取り組む遊びのひとつでありながら、手指の発達や創造力を育む大切な活動でもあります。
本記事では、保育における粘土遊びのねらいや年齢別のアイデア、安全な環境設定のポイントなどを詳しく解説します。
改めてその魅力や保育的意義を見直してみませんか?
粘土遊びが保育で人気の理由

手指の発達を促す
粘土をこねたり、丸めたり、ちぎったりする過程は、子どもたちの手指の巧緻性を育てる絶好の機会です。
とくに1〜3歳頃の子どもたちは、指先を使った動きのバリエーションが増える時期。
粘土遊びは、感触を楽しみながら手の発達を自然に促してくれます。
また、ヘラや型抜き、ローラーなどの道具を使うことで、手首や腕の運動にもつながり、操作力を高めるサポートになります。
想像力・創造力を育む
粘土遊びは、「こうしたい」「こんな形を作りたい」という思いを形にできる遊びです。
子どもたちは頭の中のイメージを粘土で表現しようとし、自然と想像力や創造力が養われていきます。
また、自分の中でテーマを見つけて「お弁当をつくる」「ケーキ屋さんごっこをする」など、ごっこ遊びに発展することも多く、遊びの世界が広がります。
集中力や情緒の安定につながる
粘土を無心でこねる行為は、大人にとってのストレス解消のように、子どもにとっても情緒の安定に繋がります。
ひとつの作業に没頭することで、集中力が高まり、達成感も味わえるため、自信の育ちにもつながります。
粘土遊びを集中して遊びこむ事が出来ると、机上に座る基礎も身についてきます。遊びから身に着けられる事は保育園だけでなく、家庭でも取り入れる事が出来ますよ。
粘土遊びの保育でのねらいとは?

全体的な計画や月案にどう位置づけるか
粘土遊びは「造形活動」の一部として年間計画や月案に位置づけられます。
以下のようなねらいで設定することが多くあります。
- 手や指を使って自由に形づくる楽しさを味わう
- 感触を楽しみながら思いを表現する
- 自分のつくったものに愛着をもち、友だちの作品にも関心を持つ
季節や行事に合わせてテーマを設定すれば、ねらいも明確になり、活動の幅が広がります。
保育指針に基づく視点
文部科学省の幼稚園教育要領や保育所保育指針では、「表現」領域において「感じたことや考えたことを自由に表現する力」を育むことが重要とされています。
粘土遊びはまさにその要素を含む活動であり、子どもの主体性や非認知能力を伸ばすのにも適しています。
年齢別・粘土遊びのアイデア

1〜2歳児向け
この時期はまず「粘土に触れる」ことが第一歩です。
・握る、つまむ、ちぎる、丸めるなど感触を楽しむことを重視します。
・「ヘビさん」「だんご」など簡単な形を見せると興味がわきます。
おすすめ素材は小麦粘土や寒天粘土。誤飲への配慮から口に入れても安全な素材が安心です。
※ただし、小麦についてはアレルギーを持っているお子さんもいるので、事前把握が大事です。園によっても異なるので取り入れる際には事前に確認する事をおすすめします!
3歳児向け
少しずつ「見立て」ができるようになる年齢です。
・フルーツやどうぶつ、顔などのテーマを決めて作ってみましょう。
・「バナナをちぎって皮をむいたよ」など、子どもの言葉と作品がつながるようになります。
道具も使い始めの時期で、ヘラや型抜きでの表現が可能です。
4〜5歳児向け
この頃になると、より具体的な表現や構成的な作品づくりが可能になります。
・ごっこ遊びと組み合わせて、お店屋さん(パン屋・レストラン)を開く
・友だちと協力して「動物園」や「街」をつくるなど、共同制作もおすすめ
作品づくりだけでなく、振り返りや発表の機会を設けることで、表現力や他者理解も育ちます。
安全に配慮した粘土遊びの工夫

素材選びのポイント
粘土遊びで特に気をつけたいのが、安全性と衛生面です。
市販の粘土には油粘土、樹脂粘土などもありますが、保育現場では以下のような素材がよく使われます。
- 小麦粘土:柔らかくて扱いやすく、安心素材
- 寒天粘土:食材由来でアレルギーにも比較的安心
- 手作り粘土:塩・小麦粉・油などで簡単に作れる
子どもが口に入れたり、肌が弱かったりする場合には、素材選びを特に丁寧に行いましょう。
遊びの前後の声かけ・衛生管理
・遊び始めに「お口に入れないよ」「遊んだら手を洗おうね」と声かけを
・粘土は人数分に分けて保管し、乾燥・汚染に注意
・使い終わった道具はしっかり洗浄・消毒を心がけましょう
アレルギーがある子への配慮も大切です。特定の素材に反応がある場合は個別対応が必要です。
粘土遊びをもっと楽しく!発展アイデア

絵本との連動で世界が広がる
粘土遊びを物語の世界と組み合わせると、さらに豊かな表現が引き出せます。
たとえば:
- 『おべんとうバス』→ 粘土でお弁当づくり
- 『しろくまちゃんのほっとけーき』→ ホットケーキをつくってみよう
- 『はらぺこあおむし』→ フルーツやあおむしを再現
物語の世界を立体的に楽しむことで、子どもたちの創造力が広がります。
季節や行事と組み合わせる
年間行事に合わせた粘土遊びもおすすめです。
- ハロウィン:かぼちゃ、おばけ、キャンディーなど
- クリスマス:リース、ツリー、サンタクロース
- 節分:鬼の顔、豆、金棒などを作って豆まきごっこへ発展
こうしたテーマを設けると、季節感のある造形遊びが楽しめ、製作展示や参観にも活用できます。
まとめ|粘土遊びで子どもの表現を引き出そう
粘土遊びは、単なる「遊び」ではなく、子どもの成長に多面的に働きかける重要な保育活動です。
- 手指の発達、想像力、集中力を育てる
- 自由な表現と達成感を味わえる
- 年齢やテーマに合わせて工夫することで、保育の質が向上
安全に配慮しながら、保育士の声かけや環境設定で粘土遊びの魅力をさらに引き出していきましょう。





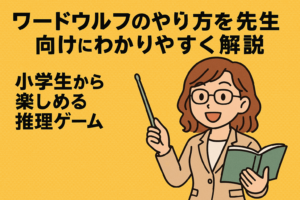
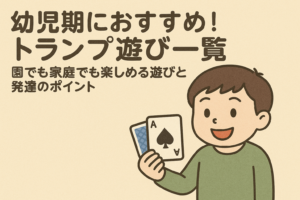
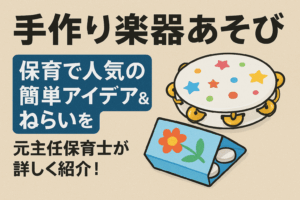

コメント